境内整備とお寺の今について
お彼岸に向けて、大安禅寺では境内整備が始まっています。
夏の暑さが残る中、草はぐんぐん伸び、草刈りや剪定作業は副住職にとって重労働です。法務の合間を縫いながら作業にあたる日々が続いています。




寺院が抱えるとされる課題
そんな折、福井新聞の記者の方がお越しになり、「現在の寺院をめぐる課題」について取材を受けました。
取材テーマは、よく耳にする「墓じまい」「寺離れ」「担い手不足」「寺院の統廃合」といった問題でした。これらは社会的にも注目され、しばしばマイナスの出来事として報道されます。
しかし副住職は、これを単純に問題視するのではなく、「なるべくしてなっている時代の流れ」として受けとめています。

お寺はお寺だけで存在しているわけではありません。
家庭の形や社会のあり方の変化とともに、檀家との関係性もまた変わっていくのは自然なことです。
実際、大安禅寺では副住職が護持管理と法務を担い、住職は金沢で他の寺院を兼務しています。こうした形は、いまやどの宗派にも見られる現実です。
「担い手がいない」のではなく、「お寺の数が現代社会にそぐわなくなってきている」と言えるのかもしれません。
寺院の成り立ちもさまざまです。
藩主が建立した寺、疫病平癒の祈祷寺、村の事情で建てられた寺──地域や時代の背景によって多様な存在理由がありました。
だからこそ、その歴史や文化財を保存・記録し、次の世代に受け渡していくことが大切です。寺院の役割は、単に建物を維持するだけでなく、その精神と文化をいかに残していくかにあると考えています。


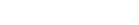



コメント