開基堂の濡れ縁解体準備
本堂の修理が無事に完成し、引っ越し準備も進むなか、
次なる修理工程として「開基堂」へとバトンが渡ります。
その第一歩として、現在は濡れ縁の解体作業が始まりました。
解体に先立って行われているのが「番付」と呼ばれる作業です。
これは、文化財修理において非常に重要な工程で、
一つひとつの木材や部材に番号(番付)を付け、
どの位置に、どのように使われていたかを正確に記録しておくためのもの。
修理後に再び元の場所へと戻すための“設計図”のような役割を果たします。



一方で、今日はもうひとつ大切な営みがありました。
大安禅寺の裏山にある歌人・橘曙覧(たちばなのあけみ)の奥墓と、その参道の掃除を行いました。
曙覧の墓は、松平家の廟所「千畳敷」の麓にあります。
最近では、天然痘の種痘に尽力された笠原白翁とあわせて、
この地を訪れお参りされる方が少しずつ増えており、
その遺徳を偲ぶ姿を見るたびに、胸の奥に温かいものが広がります。




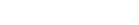


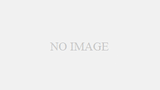
コメント