心を育てる時間
本日、大安禅寺恒例の秋彼岸会並びに放生会を厳修いたしました。
前日に搗いた御餅をお供えし、ご先祖様のご供養、そして生きとし生けるものすべての御霊へ感謝をお捧げしました。御詠歌で始まり、御檀家様とともにお経を唱え、一日を通して「支えられて生きている」ことへの感謝を届けるひとときとなりました。



こうした行事のたびに思うことは、目には見えないけれど、人として大切にすべき心を、お寺は形にして伝え遺していく場所であるということです。まさに次の世代へ継いでいくべき大切な営みだと、改めて感じさせられます。




「供養」という言葉は、サンスクリット語の「プージャ(pūjā)」に由来し、日本語では「供給資養(くきゅうしよう)」とも訳されます。つまり、ただお経を唱えるだけではなく、心を供え、心を養うことが本来の意味です。ご先祖や生き物への祈りを通して、私たち自身の心をも育てていく──供養にはそのような深い意義があるのです。









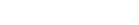



コメント